電気工事施工管理技士2級の資格を取ろうか迷っている方の中には、「結局、この資格で何ができるのかよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。現場で働くうえで有利になるのか、資格手当がもらえるのか、そもそも今の自分に必要なのか…。そうした疑問は、誰にとっても自然なことです。特に、電気工事士など他の資格との違いがはっきりしないままでは、進むべき方向に自信が持てないのも無理はありません。
この資格の本当の価値は、「何ができるか」を正しく知ることからはじまります。施工管理技士2級を持っていると、どの規模の現場で、どのような立場で働けるのか。1級との違いや、現場で実際に任される仕事の中身まで、この記事ではひとつずつ明らかにしていきます。迷いをクリアにし、自分の働き方にどう活かせるのかを見つけるための手がかりになれば幸いです。
電気工事施工管理技士2級とは?基本情報と取得方法
電気工事施工管理技士2級は、電気工事の現場において「施工管理」を行うために必要な国家資格です。施工管理とは、工事が設計通りに、安全かつ効率よく進むように計画・監督する役割を担う仕事です。電気工事士が実際に作業を行うのに対し、施工管理技士はその作業を管理する立場になります。2級の資格を持っていれば、中小規模の工事で主任技術者として配置されることができ、現場の中核を担うポジションに就くことが可能です。
この資格は国土交通省が管轄する「技術検定」によって与えられます。受験には一定の実務経験が必要で、学歴や職歴によって必要年数は異なります。例えば、高卒で指定学科を卒業している場合は3年以上、大学卒であれば1年程度の経験があれば受験資格を得られます。また、経験年数に満たない場合でも、学科試験のみを先に受ける「第一次検定」からスタートすることも可能です。
試験は年に1回行われ、一次(学科)と二次(実地)に分かれています。合格率は年度によってばらつきがありますが、全体としては比較的高めの水準で推移しており、しっかりと準備すれば十分に合格が見込める内容です。教材や講習会も多く提供されており、独学でも取り組みやすい資格といえるでしょう。
このように、電気工事施工管理技士2級は、現場の実務経験を積んだ方が「次のステップ」に進むうえで非常に現実的かつ価値ある選択肢です。現場で働きながら将来的なキャリアを広げたいと考える方には、特におすすめの資格です。
2級で実際にできる仕事とできない仕事
電気工事施工管理技士2級を取得すると、一定規模の工事において「主任技術者」として配置されることが可能になります。主任技術者とは、現場の施工計画を立て、安全や品質の管理、工程の調整、関係者との連携を担うポジションです。2級の場合、主に中小規模の建築物や施設における電気工事が対象となり、請負金額が4,000万円未満(電気工事単体の場合)であれば、元請業者として主任技術者の配置が認められています。
ただし、すべての工事に対応できるわけではありません。たとえば、請負金額が4,000万円以上の大規模工事では「1級」の資格を持つ技術者が求められます。また、施工管理技士が担うもう一つの役割である「監理技術者」になることも、2級ではできません。監理技術者とは、複数の専門工事業者が関わるような公共性の高い現場などで、安全・品質全体を統括する立場です。これには1級の資格と、さらに一定年数以上の実務経験が必要です。
また、誤解されがちですが、2級を持っていても「電気工事そのもの」は行えません。作業そのものを行うためには、別途「電気工事士」(第一種または第二種)の資格が必要です。つまり、2級は工事を“する”人ではなく、工事を“させる”人になるための資格です。現場を支えるリーダーとしての役割が中心になるため、実務だけでなく、全体を俯瞰して判断する力も求められます。
このように、2級施工管理技士には明確な「できること」と「できないこと」が存在します。自分のキャリアプランや志向に照らして、役割の違いを理解することが重要です。
1級との違いは?責任・現場対応力・待遇面まで比較
電気工事施工管理技士には「1級」と「2級」がありますが、その違いは単に等級の上下にとどまりません。現場で担える責任範囲や、企業からの評価、将来のキャリアに大きな差が生まれるため、両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。
まず最も大きな違いは、対応できる工事の規模です。1級は請負金額が4,000万円を超える電気工事でも、主任技術者としての配置が可能であり、公共工事や大規模施設の工事でも中心的な役割を担えます。一方、2級ではこのような大型案件に携わることはできず、対象はあくまで中小規模の工事に限定されます。
また、1級を取得して一定の実務経験を積むと、「監理技術者」として登録できる点も重要です。これは元請企業にとって非常に重宝される存在であり、1級保有者は採用・配置の面でも優遇される傾向にあります。逆に言えば、2級のままではこの役割には就けません。
待遇面でも違いがあります。企業によって異なりますが、1級保有者には資格手当として月2〜3万円が上乗せされるケースもあり、給与面に直接反映されることも少なくありません。さらに、1級はキャリア上位職への登用や、責任あるポジションへの推薦がされやすいという点でも、評価が大きく異なります。
とはいえ、2級を無駄に感じる必要はありません。むしろ、現場で実績を積みながら1級への足がかりとする人が多く、ステップアップを前提とした現実的な選択肢として非常に有効です。自分の現在地と目標を照らし合わせて、どこを目指すべきかを見極めましょう。
2級取得後のキャリアパスとステップアップ方法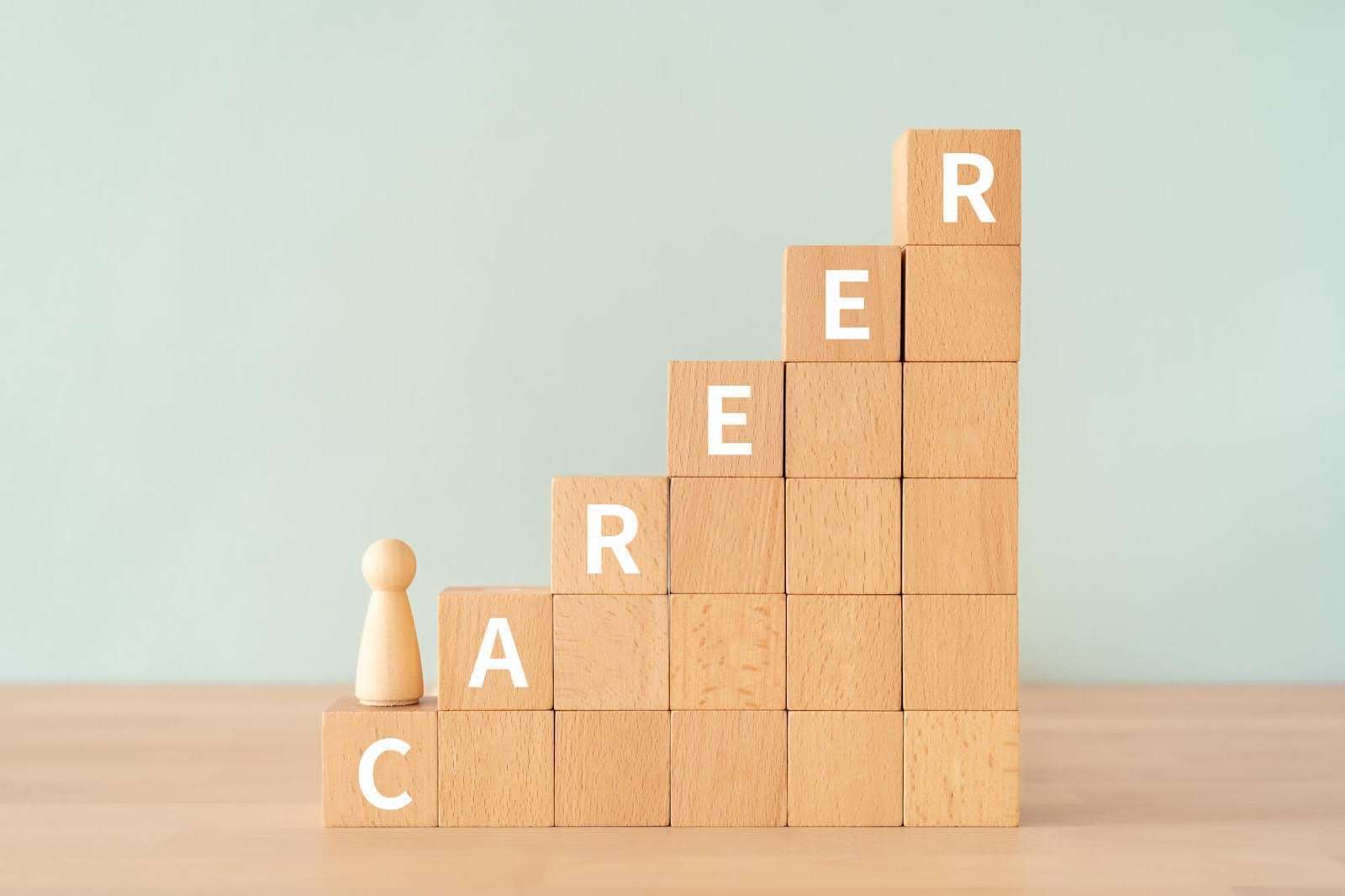
電気工事施工管理技士2級は、それ自体が現場での信頼につながる有効な資格ですが、取得後のキャリア設計によってその価値はさらに広がります。実際に多くの技術者は、2級を足がかりとして1級や監理技術者へのステップアップを視野に入れています。
まず、2級を取得することで主任技術者としての実績を積むことができます。この現場経験は、1級の受験資格を得るために不可欠です。受験には数年間の実務経験が必要ですが、2級取得後に積んだ経験は、そのまま次の資格に直結する“武器”になります。つまり、2級は終点ではなく、次のステージへの通過点と捉えるのが正解です。
さらに、電気工事士(第一種・第二種)との組み合わせによって、実務の幅も広がります。電気工事士として手を動かしながら、施工管理技士として全体を監督できる人材は、企業にとって非常に重宝されます。このように複数の資格を活用しながら、多角的に成長していけるのが電気系技術職の魅力です。
企業によっては、資格取得支援制度や講習費用の補助、実務経験を積ませるための現場配属など、キャリア形成を後押しする体制が整っているところもあります。たとえば、当社HOKUSHIN-EBAでも、2級取得者が1級を目指して実務経験を積めるよう、段階的な成長機会を用意しています。自分の力を活かせる現場で、着実にステップアップを目指す方には最適な環境です。
▶ 採用情報はこちらから
https://www.hokushin-eba.jp/recruit
現場での2級保有者の活躍事例と企業が求める役割
実際の電気工事現場では、2級電気工事施工管理技士の資格を持つ人材が要となって動いています。施工計画の立案から工程管理、資材や協力業者の調整まで、現場全体を滑らかに動かす存在として評価されているのがこのポジションです。資格があることで、単なる現場スタッフから「判断と管理を任せられる人」へと役割が変わり、チームの中心に立つことが求められます。
企業が2級保有者に期待するのは、正確な管理能力と冷静な判断力、そして周囲との信頼関係を築く力です。経験を重ねる中でそれらを実務に落とし込み、1級や監理技術者への道を開いていく人も少なくありません。現場で求められるのは、知識よりも「使える力」。2級の資格は、その第一歩として大きな意味を持っています。
資格を取ったあと、どこで、どう活かしていくか。それを考えることこそが、本当のスタートなのかもしれません。
▶ ご相談・お問い合わせはこちら


